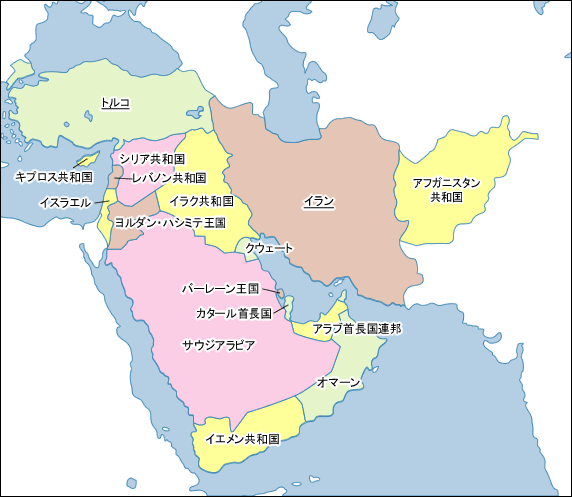大統領選の年はドル高になりやすい(ドル円相場ではなく、実効為替レート)
・強いアメリカをアピール
・選挙のある年に向けて景気浮揚を狙う経済政策でドルが買われやすい
近年はあてはまらない場合も。
ドル暴落説は本当か?
・財政赤字、ドル信用不安で暴落
・日本の失われた10年(長い不況)に陥っている
など・・
しかしドルを売って代わりに買う通貨がない。
ユーロ・・弱点が多い
円・・将来性がない
スイスフラン、金・・市場規模が小さい
マネーの行き場がないので実際にはどうか・・というところ。
介入は効果が薄れていく
①スムージングオペレーション(スムージングオペ)
急激な乱高下をおさえる
酔っ払いに水をかけて頭を冷やすようなもの。
②為替相場を特定の水準に封じ込める
物量作戦は巨額の資金が必要。
どちらも人為的な操作で長くは続かない。